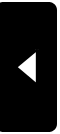2007年11月06日
変更!
バタバタしてブログのチェックをしていないうちに、
「京つう」のアドレスが変わっているではないか!
http://www.kyo2.jp/これが新しいアドレス。
「そんなふうなこと」のアドレス自体は変わってないので、
これを直接ブックマークしていただいている方は影響なかったみたいですね。
これを機会に「そんなふうなこと」をブックマークしてみては?なんちゃって。
にしても、いつも通り「京つう」を開くと「ブログが存在しません」と出るのであせりました。
京つうスタッフさん、一行目はやっぱり「移転しました」の方が親切なのでは?
ついでにもう一言いわせて(笑)。
管理画面ですが、FireFoxでもちゃんと見られるようになりませんか?
ひどいです。
こういうこと言うとなんですが、テンションさがります(笑)。
ということで、これは不本意ながらInternetExplorerで投稿しております。

「京つう」のアドレスが変わっているではないか!
http://www.kyo2.jp/これが新しいアドレス。
「そんなふうなこと」のアドレス自体は変わってないので、
これを直接ブックマークしていただいている方は影響なかったみたいですね。
これを機会に「そんなふうなこと」をブックマークしてみては?なんちゃって。
にしても、いつも通り「京つう」を開くと「ブログが存在しません」と出るのであせりました。
京つうスタッフさん、一行目はやっぱり「移転しました」の方が親切なのでは?
ついでにもう一言いわせて(笑)。
管理画面ですが、FireFoxでもちゃんと見られるようになりませんか?
ひどいです。
こういうこと言うとなんですが、テンションさがります(笑)。
ということで、これは不本意ながらInternetExplorerで投稿しております。
Posted by +0 atelier at
17:37
│Comments(5)
2007年11月04日
「半真実」
『「半真実」は、他の多くの人が寄与して残りを半分を満たし、
その結果共有の感受性をつくる器でもあるのです』
(テレンス・ライリー MoMA建築部門チーフキュレーター)
AXISの特集の中で語られた言葉ですが、今の肩書きはこれであってるのかな?
未来のデザインについて考えるといったテーマの中でした。
20世紀は真実を求めようとした。
が、もはや真実はなく、でも「半真実」みたいなものはあって、
21世紀には純粋に個人的な表現に代わって、これを再検討するようになる、
そんなふうなことでした。
おもしろい言葉ですね、「半真実」。
変な言葉ですけど、なんとなくわかるような感じしません?
すぐに「ウィキペディア」なんかが浮かんでしまいました。
え?違うって?(笑)
「イデオロギーはない、ひとつの中心というものもない、
けれどもある感受性はある」
その感受性が真実を埋める。
なんて素敵な言葉でしょうか。
その結果共有の感受性をつくる器でもあるのです』
(テレンス・ライリー MoMA建築部門チーフキュレーター)
AXISの特集の中で語られた言葉ですが、今の肩書きはこれであってるのかな?
未来のデザインについて考えるといったテーマの中でした。
20世紀は真実を求めようとした。
が、もはや真実はなく、でも「半真実」みたいなものはあって、
21世紀には純粋に個人的な表現に代わって、これを再検討するようになる、
そんなふうなことでした。
おもしろい言葉ですね、「半真実」。
変な言葉ですけど、なんとなくわかるような感じしません?
すぐに「ウィキペディア」なんかが浮かんでしまいました。
え?違うって?(笑)
「イデオロギーはない、ひとつの中心というものもない、
けれどもある感受性はある」
その感受性が真実を埋める。
なんて素敵な言葉でしょうか。
Posted by +0 atelier at
18:30
│Comments(0)
2007年11月03日
文字コード
パソコンのおかげでわからない漢字がすぐにわかるようになりましたね。
私は自称「理系」でして、漢字と歴史は苦手ですから大変助かります。
(逆に身に付かないという意見もありそうですが。)
日本工業規格で定められている漢字第一、第二水準の文字数は約6300字。
ユニコードではなんと約20000字。
すごい数。
なーんて感動していると、怒られるような論争が90年代の終わりにあったようです。
『68年革命と「文字コード」問題』と題した単文によると、
日本文藝家協会が発信元となって、「漢字を救え!」キャンペーンが行われたといいます。
これはざっくりいうと、
さっきの6000字だろうが20000字だろうが、
「諸橋大漢和辞典」に納められている約5万字に比べたら、とうてい少ない。
アメリカの企業が断りも無く勝手に決めて、
そのために「日本の文化」が「危機的」な状況に・・・うんぬんかんぬん。
そんなふうなこと。
うーん、どうなんでしょ。
逆に約5万の漢字をパソコンで使えると「日本の文化」は安泰なのかと
いじわるな言葉がすぐに頭をよぎるのですが、皆さんどう思います?
そもそも、ある言語が何らかの概念や意味を表示する「透明な記号」ではないという、
今では当たり前の学説があるのに「どうしたことか」と、
さきほどの単文の著者は批評されていました。
なるほど、たしかに。

私は自称「理系」でして、漢字と歴史は苦手ですから大変助かります。
(逆に身に付かないという意見もありそうですが。)
日本工業規格で定められている漢字第一、第二水準の文字数は約6300字。
ユニコードではなんと約20000字。
すごい数。
なーんて感動していると、怒られるような論争が90年代の終わりにあったようです。
『68年革命と「文字コード」問題』と題した単文によると、
日本文藝家協会が発信元となって、「漢字を救え!」キャンペーンが行われたといいます。
これはざっくりいうと、
さっきの6000字だろうが20000字だろうが、
「諸橋大漢和辞典」に納められている約5万字に比べたら、とうてい少ない。
アメリカの企業が断りも無く勝手に決めて、
そのために「日本の文化」が「危機的」な状況に・・・うんぬんかんぬん。
そんなふうなこと。
うーん、どうなんでしょ。
逆に約5万の漢字をパソコンで使えると「日本の文化」は安泰なのかと
いじわるな言葉がすぐに頭をよぎるのですが、皆さんどう思います?
そもそも、ある言語が何らかの概念や意味を表示する「透明な記号」ではないという、
今では当たり前の学説があるのに「どうしたことか」と、
さきほどの単文の著者は批評されていました。
なるほど、たしかに。
Posted by +0 atelier at
18:30
│Comments(0)
2007年11月02日
わがまま
最近のうるめちゃん(うちのネコの名前です)は、ちょっぴりわがまま。
もちろんそれが365%かわいいのですが、たとえばこんな感じ。
えさをあげても食べ始めません。
えさからつかず離れずでうろうろして、でも舌なめずりをします。
で、2、3粒を手にとって、手のひらから食べさせると、ようやく食べ始めます。
「食べてあげてもいいわよ」
そんな仕草を一瞬みせてから、あとはガツガツ食べて、食べたあとは、
「食べてあげたわ」
と、悪そうな顔をします。
うるめ用のお皿は古伊万里で、ふだんの私どものお皿よりかは良い待遇のはず、
そんなふうなことを考えますが、やはりネコに小判?
想いは伝わりません。
妻はこのごろ、
「わたし、最近、うるめの言うことがわかるねん」
と、進化とも退化ともとれない発言をくりかえしていますが、
一体何を語り合っているのだろうか。
えさのグレードアップ?新しいおもちゃの新規購入?
それとも中庭への外出許可?
まぁ、女性が二人そろえば、話もつきないのでしょう。
おっと、女性には失礼な発言だったかな?なんちゃて。
(えさこぼれてるで。もっとお上品に。)

もちろんそれが365%かわいいのですが、たとえばこんな感じ。
えさをあげても食べ始めません。
えさからつかず離れずでうろうろして、でも舌なめずりをします。
で、2、3粒を手にとって、手のひらから食べさせると、ようやく食べ始めます。
「食べてあげてもいいわよ」
そんな仕草を一瞬みせてから、あとはガツガツ食べて、食べたあとは、
「食べてあげたわ」
と、悪そうな顔をします。
うるめ用のお皿は古伊万里で、ふだんの私どものお皿よりかは良い待遇のはず、
そんなふうなことを考えますが、やはりネコに小判?
想いは伝わりません。
妻はこのごろ、
「わたし、最近、うるめの言うことがわかるねん」
と、進化とも退化ともとれない発言をくりかえしていますが、
一体何を語り合っているのだろうか。
えさのグレードアップ?新しいおもちゃの新規購入?
それとも中庭への外出許可?
まぁ、女性が二人そろえば、話もつきないのでしょう。
おっと、女性には失礼な発言だったかな?なんちゃて。
(えさこぼれてるで。もっとお上品に。)
Posted by +0 atelier at
18:30
│Comments(0)
2007年11月01日
平和の代償
「いったい何人殺してきたのだろうか。
武装解除の瞬間、ほとんどの少年は泣く」
(「武装解除」伊勢崎賢司 講談社現代新書のオビより)
この本は、著者の伊勢崎賢司が国連のDDRという活動で、アフリカで内戦中の極貧国に
武装解除させた時のことなどを書いたもの。
日本人がそんなところで、そのエリアの責任者となって、
武器も使わず、話し合いと交渉だけで(正確には莫大な費用もかけて)、
武装解除をしたということ自体に驚きません?
このアフリカの極貧国とは、シエラレオネという聞いたこともない国。
ここでの反政府ゲリラの残虐行為(生きたまま子どもの手足を切断する)の犠牲者は数千人。
十年間の内戦での犠牲者は5万人とも50万人ともいわれているとのこと。
この時の武装解除では、これら残虐行為の指導者に対し、罪は一切問わない、
それを行った兵士にも罪を問うことがないという条件で成立したそうです。
そんなひどいことをしたやつらに罪を問わない?
そんなばかな!正義はどこへ?!そんなふうなこと思いませんでしたか?
けれど著者はいいます。
「これが平和の代償であった」と。
つまり、「正義」より「平和」だということです。
文中こんなことも語られていました。
「(内戦で)生き残った人は、和解に人間的な価値を見出して、和解するのではない。
和解を善行として、和解を受け入れるのではない。
復讐の連鎖を心配するのでもなく、「絶望」から和解するのだ」
(ちょっと話が暗すぎたかなぁ。そんな日もありね。)

武装解除の瞬間、ほとんどの少年は泣く」
(「武装解除」伊勢崎賢司 講談社現代新書のオビより)
この本は、著者の伊勢崎賢司が国連のDDRという活動で、アフリカで内戦中の極貧国に
武装解除させた時のことなどを書いたもの。
日本人がそんなところで、そのエリアの責任者となって、
武器も使わず、話し合いと交渉だけで(正確には莫大な費用もかけて)、
武装解除をしたということ自体に驚きません?
このアフリカの極貧国とは、シエラレオネという聞いたこともない国。
ここでの反政府ゲリラの残虐行為(生きたまま子どもの手足を切断する)の犠牲者は数千人。
十年間の内戦での犠牲者は5万人とも50万人ともいわれているとのこと。
この時の武装解除では、これら残虐行為の指導者に対し、罪は一切問わない、
それを行った兵士にも罪を問うことがないという条件で成立したそうです。
そんなひどいことをしたやつらに罪を問わない?
そんなばかな!正義はどこへ?!そんなふうなこと思いませんでしたか?
けれど著者はいいます。
「これが平和の代償であった」と。
つまり、「正義」より「平和」だということです。
文中こんなことも語られていました。
「(内戦で)生き残った人は、和解に人間的な価値を見出して、和解するのではない。
和解を善行として、和解を受け入れるのではない。
復讐の連鎖を心配するのでもなく、「絶望」から和解するのだ」
(ちょっと話が暗すぎたかなぁ。そんな日もありね。)
Posted by +0 atelier at
19:42
│Comments(0)